初めに

私はフラメンコの仕事を通して、長い時間スペインとスペイン人を見てきました。
日本人と通じる場面もあれば、まったく正反対だと戸惑うこともあります。心から打ち解けて付き合えることもあれば、正直に言って、強いストレスを感じたこともありました。まあ日本人相手でも同じですが、それは多分に、私自身の語学力の至らなさや度量の小ささによるものだと思います。それでもなお、そうした距離感の背景には、彼らのカトリックという宗教的な土壌があるのではないか。私は長いあいだ、そんな思いを抱いてきました。
私の「スペイン人を知りたい」「カトリックというものを知りたい」という気持ちは、一時的な関心ではなく、時間をかけて静かに育ってきたものです。
世界を見ていくと、宗教は個人の信仰の問題であると同時に、政治や経済、さらには争いとも深く結びついた存在として立ち現れます。日本に戻り、新興宗教の問題などについて考えるとき、「宗教とは何か」を探ることは、私にとっていつの間にかライフワークのようなものになりました。
キリスト教が日本にもたらされた過程と、フラメンコが日本に受け入れられていった過程とを重ねて考えると、どこか共通するものがあるように感じられます。外から来た宗教や文化が、その土地の価値観や生活と出会い、姿を変えながら根を下ろしていく。その過程そのものに、私は以前から強い関心を抱いてきました。
こうした思索の延長線上で、潜伏キリシタンという存在に向き合うことになり、潜伏キリシタンに関する本にも手を伸ばしました。しかしそこに描かれる世界はあまりにも救いがなく、しばらく言葉を失いました。純粋な信仰を抱く人々の背後に、欲や金、権力が見え隠れする。その構図は、時代や場所を越えて繰り返されてきた人間の姿なのかもしれません。
先日私は、潜伏キリシタンの里とされる長崎・外海(そとめ)を、この目で見てきました。切り立つ海岸線と美しい海が広がるその地で、かつて苛烈な弾圧の歴史があったことを思うと、その風景と背後にある歴史との落差が強く印象に残りました。
この文章では、私自身の感情や評価はできるだけ抑え、潜伏キリシタンとはどのような人々だったのか、その輪郭をたどっていきたいと思います。外から持ち込まれた宗教が、日本という土地でどのように受け止められ、変容し、生き延びてきたのか。その一端を、外海の風景とともに静かに記しておきたいと思います。
潜伏キリシタンと隠れキリシタン

「潜伏キリシタン」とは、江戸時代の禁教政策のもとで、キリスト教の信仰を公にすることができず、密かに祈りを続けた人々のことを指します。キリスト教が禁じられていた時代、日本では信仰を持つことそのものが大きな危険を伴っていました。信仰を捨てることもできず、かといって国外へ逃れる道もなかった人々が選んだのが、表に出ないという生き方でした。
一般には「隠れキリシタン」という言葉がよく知られていますが、この呼び方は、禁教下の時代と、その後の時代とをまたいで使われています。禁教の時代、公に信仰を表すことができずに祈りを続けていた人々は「潜伏キリシタン」と呼ばれます。この潜伏キリシタンの時代は、1614年の徳川幕府による禁教令から、1873年の明治政府による禁制解除まで、およそ260年間に及んだとされています。そして禁教が解かれた後、カトリックに復帰した人々がいた一方で、復帰せず、潜伏の時代に形づくられた信仰のあり方を守り続けた人々もいました。そうした人々は、現在では「隠れキリシタン」と呼ばれています。
禁教下で潜伏していたキリシタンと、その信仰を受け継いだ隠れキリシタンは、教会や※司祭を持たず、祈りを日々の暮らしの中に溶け込ませていきました。祈りの言葉は口伝えで受け継がれ、意味が分からなくなっても、音や形として大切に守られていきます。マリア像は観音像の姿を借り、信仰は仏教や民間信仰と混ざり合いながら、人目につかないかたちで続いていきました。
そこでは、教義を正確に守ることよりも、祈りを絶やさないことそのものが何より大切だったように思われます。潜伏キリシタンの時代から、隠れキリシタンの時代へと連なっていくその歩みは、日本という土地の中で、外からもたらされた宗教が姿を変えながら生き延びてきた過程そのものだったのではないでしょうか。
※司祭
カトリックでは、司祭と呼ばれる聖職者がミサを執り行います。ミサとは、パンとぶどう酒を用いた祈りを中心とする儀式で、信仰生活の中核をなすものです。
外海(そとめ)という場所
長崎市の中心部から車で北へ向かい、山道を抜けた先に外海があります。市街地の賑わいから切り離されたようなこの土地は、山と海に挟まれ、集落が点在しています。切り立った海岸線と広い海を前にすると、ここが長いあいだ人の出入りが限られていた場所であったことが、肌で感じられます。

外海を案内してくれたタクシーの運転手さんは、潜伏キリシタンの末裔だと話してくれました。山道を進みながら、「ここまでは、役人も歩いて来るのが大変だったでしょう」と、何気ない口調で言います。その一言で、この土地が持っていた距離と隔たりの重さが、現実のものとして迫ってきました。
外海は、遠藤周作の小説『沈黙』の舞台の一つとしても知られています。小説の中で描かれる厳しい自然と沈黙の時間は、決して誇張ではなく、この土地そのものから立ち上がってきたものなのだと感じられました。


私は、サン・ジワン枯松神社を訪れました。ここは、宣教師サン・ジワンが実際に潜伏していたとされる場所です。山の奥まった静かな場所にあり、容易には人目につかないことが想像できます。周囲の気配をうかがいながら、息を潜めて暮らしていた日々を思うと、足元の土の感触が重く感じられました。
禁教が解かれた後、外海にも、素朴ながら美しい教会がいくつも建てられました。けれども、その教会に、いわゆる隠れキリシタンの人々は、信仰を胸に抱いたまま、姿を見せることはなかったのではないか。そんな想像が、この土地の静けさの中で、自然と浮かんできました。
外海は、潜伏キリシタンが生きた場所であり、そして隠れキリシタンという選択が生まれた場所でもあります。美しい海と厳しい山に囲まれたこの土地は、信仰を語らず、ただ抱えて生きるという時間を、長く受け止めてきたのだと思います。
祈りの痕跡

外海を歩いていると、ここに生きた人々の信仰は、教えや言葉としてよりも、痕跡として残っているように感じられます。目に見えて信仰を示すものはほとんどありません。けれども、風景の中や暮らしの気配の中に、かすかな「祈りの名残」が感じ取れる場面がありました。
外海を案内してくれたガイドの方は、「民家を利用した、いわば秘密教会のような場所もあったでしょうね」と、何気ない調子で話してくれました。はっきりとした記録が残っているわけではありませんが、そうでなければ、260年間もの間祈りを続けることは難しかったはずだ、と。その言葉を聞き、外からはごく普通に見える家の中で、声を潜めながら祈りが捧げられていた光景が、自然と想像されました。
墓地に残る小さな石も、そうした祈りの痕跡の一つです。祈るときだけ石を十字の形に並べ、終わればまた崩す。誰の目にも残らないように工夫された、そのささやかな所作に、信仰を表に出さずに守り続けてきた人々の切実さが感じられました。
潜伏キリシタン、そしてその後の隠れキリシタンの人々にとって、信仰は公に語るものではありませんでした。教会も司祭も持たないまま、祈りは家の中や日々の暮らしの中に溶け込み、静かに受け継がれていきました。外から見れば何も残っていないように見えても、その沈黙の中にこそ、彼らの選択が刻まれているように思えます。
遠藤周作『沈黙』について
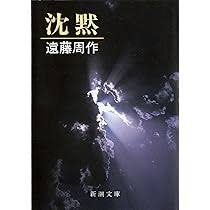
外海を旅しているあいだ、私は遠藤周作の『沈黙』を読みました。切り立つ海岸線や、人の気配が薄れていく山道を前にすると、物語の舞台が抽象的な「過去」ではなく、具体的な場所として立ち上がってくるように感じられました。
不思議なことに、『沈黙』は落ち着いて最後まで読むことができました。重い題材を扱った作品であるにもかかわらず、外海の風景と重ねることで、物語の痛みや問いを、過剰な感情ではなく、静かな思索として受け止められたように思います。
『沈黙』という題名は、一般に「神の沈黙」を指していると理解されています。迫害の中で苦しむ人々の前で、神が何も語らず、何も介入しないように見える。その沈黙に、人はどう向き合うのかという問いが、物語の根底に流れています。
しかし外海を歩きながら読み進めるうちに、その沈黙は、単に神が不在であるということではなく、人間がその沈黙をどう受け止め、どう生きるのかを問う時間でもあるように感じられました。声にならない祈りや、表に出せない信仰が、この土地の風景と重なり合いながら、物語の中に静かに息づいているように思えました。
信徒発見と禁教解除

明治に入ってからも、キリスト教の禁教がすぐに解かれたわけではなかったことを、私は今回初めて知りました。
大浦天主堂を訪れた際、私は「信徒発見」が起きたその場所に立ち、鳥肌が立つほどの衝撃を受けました。勇気をもって信仰を打ち明けた人々の行動には胸を打たれますが、その直後に待っていたのが大規模な弾圧だったことを知ると、複雑な気持ちです。
その後の歴史の展開も、多くのことを考えさせられるものでした。欧米諸国からの強い抗議を受け、明治政府は最終的に禁教を解き、信仰の自由を公式に認めることになります。潜伏キリシタンの人々が再び表に出るまでの道のりには、多くの犠牲と葛藤がありました。同時に、外圧や国際関係といった要因が深く関わっていたことも見えてきます。
この出来事を振り返ると、それが単なる宗教上の問題にとどまらず、政治や社会、さらには国際情勢とも切り離せない出来事であったことを、改めて実感します。
信徒発見
1865年、大浦天主堂で、長いあいだ潜伏していたキリシタンたちが、フランス人司祭に自ら信仰を打ち明けました。この「信徒発見」は、禁教下で密かに受け継がれてきた信仰が、約250年の時を経て姿を現した出来事でした。
隠れキリシタンのその後と現代

禁教解除後、潜伏キリシタンたちはそれぞれの選択をしました。カトリックに復帰した人々もいれば、独自の信仰を守り続けた人々もいました。後者は、いわゆる「隠れキリシタン」と呼ばれ、日常生活の中で祈りを続けながらも、表に出ることはほとんどありませんでした。
私は資料館で、隠れキリシタンの「最後のクリスマスの儀式」の映像を見ました。映像から伝わるのは、形式や手順を正確に行うことを何よりも重んじる姿勢です。後継者がいなくなるため「最後の」ということになっているようです。儀式の意味や神学的な色彩よりも、繰り返しを守ること、形を絶やさないことが第一義であることがわかりました。その印象は、非常に日本的とも言えるもので、キリスト教色はむしろ感じられませんでした。信仰の内容よりも、形や手順を守ることに価値を置く――その姿勢が、潜伏時代から連綿と受け継がれてきたのだと思います。
現代の隠れキリシタンの状況を見ると、その伝統は脈々と続いているものの、かつてのような共同体はほとんどありません。長崎や五島列島、外海などの地域では、独自の信仰を受け継ぐ人々はごく少数となり、高齢の信徒が中心です。こうした状況の中でも、家々の中で密かに祈りを守り、祭りや儀式を行うことで伝統を維持しているようです。
こうして現代にまで受け継がれる姿を見ると、信仰は必ずしも目に見える形で存在するわけではないけれど、生活の中にしっかり根を下ろしていることがわかります。それは、外海の風景や祈りの痕跡と同じく、語られない歴史の時間が形として残っている証でもあるのです。
心に残っていた音楽
外海を訪れる以前から、私の心の奥に残り続けていた音楽があります。ここに挙げる二つの映像と歌です。特に二つ目の曲は、セビージャの石畳の路地や教会の前で何度も耳にしました。
そのたびに、言葉では説明できない感情が胸に広がりました。美しい旋律と声が、人の心に直接触れてくるような感覚です。こうした音楽の力が、人々をカトリックへと強く引き寄せてきたのではないか。そんな想像が、ごく自然に浮かびました。信仰と結びついた音楽や芸術は、理屈を超えて人の内側に入り込み、深い共感や帰属意識を生み出します。その意味で、それらは信仰を広めるうえで、大きな役割を果たしてきたのだと思います。
一方で、その力が歴史の中で、結果的に人々を苦しめる方向へと使われてしまった場面があったことも、また事実です。感動を生むものが、必ずしも幸福だけをもたらすわけではない。そのことを思うと、心を動かされた記憶と拭いきれない疑問とが静かに重なります。
外海を歩きながら、私はその相反する思いを、再びかみしめました。
参考映像・音楽
おわりに

外海を歩き、『沈黙』を読み、そして現地で話を聞くなかで、私の中にはいくつもの思いが交錯しました。幕府が禁教に踏み切った事情も、単純な「悪」として切り捨てられるものではないように感じられます。一方で、信仰を広めようとした側も、その熱意が結果として人々を深い苦しみに追い込んだことは否定できません。
歴史を振り返ると、人間は宗教に限らず、理念や正義の名のもとに、驚くほど容易に残酷な行為へと踏み出してしまいます。その姿は、場所や時代が変わっても繰り返されてきたように思えます。
外海の静かな風景の中に立っていると、神がいるかいないかを断定することよりも、人が何を信じ、何のために行動してきたのかを見つめることの方が、私には大切に思えました。信仰もまた、人間が生み出した想像力や希望、そして弱さの表れなのかもしれません。
この旅を通して、私は何か一つの答えを得たわけではありません。ただ、潜伏キリシタンや隠れキリシタンの生き方、そして外海という土地が抱えてきた時間に触れながら、「人はなぜ信じ、なぜ争ってしまうのか」という問いを、以前よりも静かに考えられるようになった気がしています。
教室について
当教室では、フラメンコの踊り、カホン、パルマのレッスンを行っています。
あわせて、カンテ、スペイン語、スペイン文化に関する内容も、付随する形で扱っています。
レッスンの詳細(内容・日時・形式等)については、個別にご案内いたします。
お問い合わせは、下記よりお願いいたします。
お電話でのお問合せは
090-9207-4070
Eメールは
mail@flamenco-mari.com
LINEは

担当:三浦




